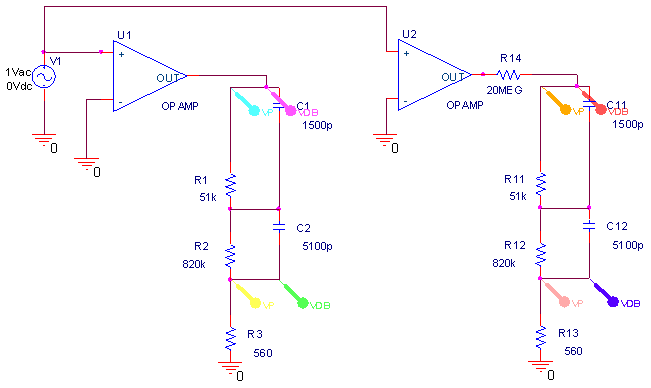
電圧利得120db、出力インピーダンス=0Ω、周波数特性が∞にフラット(=時定数が0個)のほぼ理想的なオペアンプでRIAAイコライザー回路をドライブする。NF型イコライザーではこの回路がNFB素子になる。
左が電圧出力アンプドライブ。右はオペアンプ出力にシリーズに20MΩの抵抗を挿入し電流出力アンプドライブにしたもの。
アンプ出力電圧とその位相、NFB素子通過後のR3(R13)における電圧=帰還電圧とその位相を観る。
両方の結果を一挙に表示したのでちょっと見にくい。が、中央に横に倒したひょうたんのようになったグラフが完全に線対称であることが分かる。そのために敢えてこうしてみたのだ。
次に電圧出力の場合と電流出力の場合を別々に表示する。
最初に電圧出力アンプ。
グラフ上から、縦軸120dbのところにある直線がアンプ出力の電圧利得である。
電圧利得120dbのオペアンプ入力に1VACを入力したので、出力の電圧利得は正に120dbとなる。周波数特性無限大のオペアンプであるから、現実の場合のように高域で電圧利得が小さくなるということがない。だから横一線の直線となる。
次に、右上がりとなっている線がNFB素子通過後のR3における電圧利得。これが即ちNFB回路の帰還電圧だ。その利得は10Hzで約57dbであり、周波数とともに上昇して1MHz付近でアンプ出力電圧利得と同じ120dbとなる。
この帰還電圧の特性がNFB帰還回路で作った逆RIAA特性だ。
だからこの帰還電圧をアンプの反転入力に加えるとアンプクローズド電圧ゲイン特性がRIAA特性となるのだ。それが、ここではアンプ出力電圧から帰還電圧を引いてその状態をシミュレーションした、グラフで右下がりになっている線。
このように、電圧出力アンプでNF型によりRIAAイコライザー特性を得るためには、NFB量は高域ほど逆RIAA特性で多くなるのが必然なのだ。1MHzではNFB帰還量はアンプの利得とイコールになっているから、即ち100%帰還ということになり、結果クローズドゲインは0dbとなる。グラフのとおりだ。
これが第1点。
次に、中央で2つの山をなしているのが帰還電圧の位相である。
最後に、0dbのところの直線がアンプ出力電圧の位相だ。
このオペアンプは周波数特性∞の完全電圧出力アンプであるから、その出力電圧の位相は揺るぎなく0°。だから、山をなす帰還電圧の位相は完全にNFB回路自体の位相特性である。
「オーディオDCアンプ製作のすべて 上巻」のP81、第20図にβの周波数特性と位相特性の実測データが掲載されているので、これと見比べてみよう。
全体的に進み位相であり、150Hzに63°、20KHzに81°のピークがあり、42Hzから230KHzにかけて(実測では32Hzから100KHzにかけて)位相が+45°を越えている。と、ほぼ同じ結果である。
電圧出力アンプでNF型でRIAAイコライザー特性を得ると、NFB帰還電圧の位相は必然的にこのような進み位相になる。
これが第2点。
この2点が、“理想NF型イコライザー”から見た場合の従来のNF型イコラーザーの欠点ということになる訳だ。
ただし、これで帰還電圧の位相が180°以上も回るということではないから、発振等のNFBに伴う分かりやすい問題を生じるものではない。ので、実用上は問題ない。のも事実ではある。
が、
電流出力アンプ。
電圧出力アンプでNF型イコライザーを構成した場合のこのふたつの非理想的状態が完全に理想的になる、という魔法のようなことが電流出力アンプでNF型イコライザーを構成すると可能になる。
グラフの一番上が電流出力アンプの出力点における電圧利得。なるほど。アンプ出力の電圧利得特性がそのままRIAA特性となっている。
そして、グラフの縦軸29dbのところにある直線がNFB回路通過後のR13における電圧利得=帰還電圧の特性なのである。
なんと、NFB量が周波数にかかわらず一定となるのだ。
これが第1点。
アンプ出力電圧から帰還電圧を引いてクローズドゲイン状態をシミュレーションしたのが、10Hzで64db付近から右下がりになっている線であるが、以上から当然の結果としてそれはアンプ出力電圧利得特性の線を平行移動したRIAA特性になっている。
では、問題の帰還電圧の位相特性はどうか。
それは、グラフの縦軸0°のところでほぼ直線の線が帰還電圧の位相なのである。帰還電圧の位相がなんと周波数にかかわらず全域で0°なのだ。
これが第2点。
この2点、すなわち、全域で周波数にかかわらず一定量のNFBがかかり、しかもNFBの位相が全域で入力と位相差0°である。という正に理想的なNFBが実現されている。
これが理想NF型イコライザー。
では、電圧出力の場合に帰還電圧に現れた位相ズレはどこにいったのか?
それはアンプ出力点における位相の遅れとして現れる。それがグラフ一番下の2つの谷をなしている線だ。
これは、電圧出力アンプの場合の帰還電圧の位相特性と完全に線対称である。
NFB回路入力点においての遅れ位相が、それと全く線対称のNFB回路の進み位相によってキャンセルされ、NFB出力電圧位相=帰還電圧位相は0°になってしまう。
これが理想NF型イコライザーの仕組み。というわけだ。
素晴らしい。
が、この世の現実界にある以上、やはり理想と現実の問題を考えなければならない。
イデアならぬ現実界には出力インピーダンスが無限大の電流出力アンプはない。上のシミュレーションでもその出力インピーダンスは20MΩである。現実のアンプを作る場合、アンプ出力に20MΩの抵抗を入れる訳にはいかない。20MΩの出力インピーダンスを有する電流出力アンプも現実にはなかなか困難だろう。
だから、出力インピーダンスが20MΩより低くなった場合はどうなるのか、が問題だ。
パラメトリックにR14を20MΩ、10MΩ、5MΩ、2.5MΩ、1.25MΩ、625KΩ、312.5KΩと変更して、理想と現実を観る。
どのグループも下から20MΩ、10MΩ、5MΩ、2.5MΩ、1.25MΩ、625KΩ、312.5KΩの場合。
このNFB素子の定数でほぼ理想的な状態とするためには20MΩの出力インピーダンスが必要なのだ。ということが分かる。
10MΩでは最大2°、5MΩでは4°、2.5MΩでは8°、1.25MΩでは14°、625KΩでは22°、312.5KΩでは32°、帰還電圧の位相が進む。
合わせて帰還電圧自体も全域一定から、低域においてより減少してしまう。
要するに次第に電圧出力アンプに近づくということだ。
理想はそう簡単には実現しない。という現実がここでも分かる訳だが、これでも電流出力アンプでNF型イコライザーを構成すれば、電圧出力アンプでNF型イコライザーを構成した場合に比較し遥かに理想的な状態が得られる。ということは明らかだ。
続いて、周波数特性が∞にフラット(=時定数が0個)という非現実的な条件から離れ、高域特性に限界を有する普通のアンプをモデルに、さらに現実界の足元を観る。
先ずは電圧出力アンプによるNF型イコライザー
回路は、21年前のNo−69“最新超高速SWレギュレーター採用DCプリアンプ”のファーストイコライザーである。
今とは異なり、抵抗負荷の2段差動アンプ+プッシュプルエミッタフォロアの構成である。これがK式第1世代の構成であるが、初段、2段目の定電流回路と初段のカスコードアンプが付加され、ほぼ第1世代の最終型だ。
使用トランジスタは別物だがモデルがないのでやむを得ない。が、シミュレーション上は問題ない。また、評価版の制限から初段定電流回路は電流源で代用してある。
2段目差動アンプの出力インピーダンスはほぼその負荷抵抗15KΩに等しい。これが終段のプッシュプルエミッタフォロアによって低下し、アンプ出力では無帰還時でも低域で数十から数百Ω程度の出力インピーダンスとなるであろう。したがって、NFB帰還素子のインピーダンスとの相対的関係から電圧出力アンプである。
NFB回路の1500pFにシリーズに抵抗が挿入されているが、NFBに伴う発振等の分かりやすい問題を回避するために必要な抵抗だ。これも理想と異なる現実への対応。その効能も探るためにシミュレーターのパラメトリック解析機能により、その抵抗=R13を0Ω、1.2kΩ、2.4kΩ、3.6kΩとした場合を一挙に観る。
一番上のグループがNFB回路出力点における電圧の位相。
やはり2カ所のピークがある進み位相になっている。のは、電圧出力アンプでドライブしていることの証だが、上の周波数特性∞の理想的オペアンプでドライブした場合と多少の違いがある。
低域側は150Hzに61°、は、上の完全電圧出力アンプの場合に同じだが、高域側は20KHzより低い9KHz付近で61°程度のピークとなっている。線は4本あり、上からR13が0Ω、1.2KΩ、2.4KΩ、3.6KΩの場合だが、高域側のピークはR13の抵抗値が大きくなるほどに周波数が下がり、ピークも僅かに小さくなることが分かる。
また、周波数特性が無限大の理想的OPアンプの場合との最大の違いは、可聴帯域以上の高域における位相が0°を越えて大きく遅れ位相に回転してしまっていることだ。こちらは周波数特性に高域限界を有する現実のアンプなのである。
上から2番目のグループがアンプ出力の電圧利得。低域では74db程度だが、これが10KHz付近から減少に転じている。要するに高域に時定数があるために有限の周波数帯域しかないのだ。これが現実だ。そしてこれが現実のアンプを使った場合に帰還電圧が高域で0°を越えて遅れ位相に回転してしまう理由なのだ。
現実はこうなのだが、高域で位相が遅れてしまうとなると、安定にNFBを掛けるためには位相が180°回転する前にループゲインを1以下に沈めてしまわなければならない。という制約が課される。
この制約に対応するためには、理論的にか経験則からかループゲインが1になるポイントの遅れ位相を120°以内にすればとりあえず大体は安全ということになっているらしい。
そこで、その下のXの如く交差している線のうち、左下から右上に上がっていくグループがNFB回路出力点における電圧利得=帰還電圧なのだが、高域で4本に分かれ上からR13が0Ω、1.2KΩ、2.4KΩ、3.6KΩの場合なのである。0Ω(すなわちRなし)の場合高域で帰還電圧がアンプ出力電圧に等しくなるのだが、R13をここにシリーズに挿入することによって高域での帰還電圧を制限している、ということである。
すなわち、左上から右下に下がっていく線のグループがアンプ出力電圧から帰還電圧を引いてクローズドゲイン状態をシミュレーションしたものということになるのだが、このR13による高域帰還電圧の制限効果によって、R13=0Ωの場合高域でクローズドゲインが0dbになるところ、R13の値が大きくなるほどに高域でも利得を有するものとなり、R13=3.6KΩでは18db強のゲインを持つことになる、ということなのだ。
結果、その分、クローズドゲインの周波数特性が20KHz以上の高域でRIAA特性から外れることが分かるのだが、ここまでのレベルであれば可聴帯域上限の20KHzまでのRIAA特性を保ったままで、NFB安定性確保のための対策になるということなのである。
そのポイントは、オープンゲインがクローズドゲインにクロスするポイントでの帰還電圧の位相だ。
アンプオープンゲインの電圧利得特性と帰還電圧の位相特性を見た場合、R13=0Ω即ちR13を挿入しない場合は、超高域でアンプのクローズドゲインは0dbとなることから、アンプオープンゲインが0dbになる周波数ポイントを見ると55MHz付近である。その点での帰還電圧の位相は−230°にも達しているから、これでは必ず発振してしまうであろうことが分かる。
R13=3.6KΩを挿入することによって、超高域でもクローズドゲインが18dbとなって、オープンゲインが18dbとなる周波数は15MHzとなるので、そのポイントにおける帰還電圧の位相をみると−135°程度となっている。安全域の−120°を越えているが、これでギリギリ発振するかしないか程度の位相余裕が得られるわけだ。
が、これでも位相余裕が少ないので、かりに発振しなくとも場合によって発振しやすいであろう。例えば、出力に容量負荷がぶら下がったような場合には、簡単に発振してしまうということなのだ。実際、テスターの微少な内部容量が繋がっただけで発振してしまう場合があるので、アンプオフセットを調整するためにテスターを出力に繋ぐ場合は、発振しないようにテスター棒の先に数KΩ程度の抵抗を繋いでやるべし、ということだった。のはこういう訳だ。
NF型イコライザーは、高域でNFB量が増大するからNFB安定性を確保することが難しいので対策を講じる必要がある、ということの理屈はこういうことであり、1500pFにシリーズに入れる抵抗R13はその対策であり、その効果はこういうことなのだ。
が、理想NF型イコライザーの視点で見ると、周波数によりNFB量が異なる(高域ほどNFB量が多い)点はどうにもならないが、帰還電圧の位相のずれは、アンプ自体の高域限界による位相遅れとNFB素子による位相進みが相殺されることにより、可聴帯域内での高域側の位相ずれがかえって小さくなっている、ということも事実として見ておく必要がある。
すなわち、ここでは非理想的状態が故に逆に理想的状態に近づいているので、まぁ、怪我の功名というべきものなのだが、R13=3.6KΩの状態で、位相が45°を越える範囲は45Hzから10KHzと、理想OPアンプで電圧ドライブした場合より理想に近くなっているのである。
さて、この時期は、アッテネータの50KΩがアンプの負荷となっていた。低出力インピーダンスの電圧出力になっているので影響はないと思うが、確認のためアンプ出力に50KΩを繋いでみる。
全く同じだ。
電圧出力アンプであるから、こうでないとおかしいということではある。
分配型イコライザー方式はどうか。
分配型イコライザー方式とはRIAAイコライズ機能の低域上昇と高域下降を2つのアンプで別々に行う方式。その効能は帰還電圧の位相ずれがより少ない状態になるということだったのだが、それを確認してみる。
あわせて超高域における位相的なNFB安定性の面でも有利なのではなかろうか、と思えるのでその点も確認してみる。
先ずはファーストイコライザー。こちらは低域上昇を担当する。
帰還電圧の位相が、低域150Hzで最大60°程度の進み位相になるのは同じだ。
高域側の山は当然なくなるのだが、アンプの高域限界により4KHz以上では遅れ位相になる。上の場合の高域側の進み位相の山が小さいのは、アンプ側の高域限界による遅れ位相が加わるからであることがこれで明確だ。
これで、帰還電圧の位相が45°を越えるのは45Hzから400Hzまでである。
RIAAの高域下降側のイコライザー機能を有しないので、1KHz以上でも43.5dbのクローズドゲインを有することになる。のが上の場合との大きな違いだ。
オープンゲインが43.5dbとなるポイントの帰還電圧の位相は−105°弱である。結果、上の場合に比べ分配型にしたことにより、ファーストイコライザーは位相的に遥かに安定である。ということになる。
だから、このアンプの場合は2段目差動アンプTRのCobが第1ポールを形成しているので手の入れようはないが、例えば2段目にカスコードアンプを付加して外付けコンデンサーで位相補正するようにすれば、分配型イコライザータイプとした場合のファーストイコライザーの位相補正コンデンサーの容量は、通常型イコライザーの場合よりかなり少量で済む筈だ。な〜んて、第2世代のGOAアンプ以降はその方向に進んだ訳ですね。(^^)
次にセカンドイコライザー。こちらは高域下降を担当する。
状況はこれまでの結果で大概分かるので、帰還電圧制限抵抗R8は1.2KΩに固定して観る。
帰還電圧の位相は勿論低域で山になることはなく、高域で5.5KHzに50°をピークとする山ができるものとなった。
位相が45°を越える範囲は3KHz〜9KHzである。
ファーストイコライザーの方が45Hzから400Hzであったから、分配型イコライザーの場合、帰還電圧の位相が45°を越える範囲は45Hz〜400Hz&3KHz〜9KHzと、確かに通常タイプより狭い範囲になる。
やはり、帰還電圧の位相ずれがより少ない範囲に収まるという意味で、分配型イコライザー方式は通常タイプより理想に近い。ということが分かる。
さて、高域帰還電圧制限抵抗の働きにより、高域でもクローズドゲインは8dbとなる。
オープンゲインが8dbとなるポイントは9MHzであり、そのポイントでの帰還電圧の位相は−123°程度であろうか。これなら安全範囲であろう。
通常型では制限抵抗値を3.6KΩにしても−135°であったから、分配型はNFB安定性という意味でも通常型より有利であるということになる。予想どおりだ。
これがプリアンプの出力になるので、容量負荷耐性も探る。
容量負荷安定性を図るためにということで、この出力には47Ωが挿入されているのである。その効果はいかなるものなのだろうか。
出力にシリーズの抵抗47Ωの先に容量負荷を繋いで超高域の位相の動向を観る。
負荷容量はパラメトリックに100pF、200pF、400pF、800pF、1600pFである。2497を10m伸ばすと700pF程度になることを想定したもの。
容量が大きくなるほどに帰還電圧の位相回転は早くなる。が、その程度はそう大きいものではない。また、負荷容量が大きくなるほどにオープンゲインが8dbに沈むポイントも低くなるために位相的な安定性は確保される、と見て良さそうだ。
同様のことを出力にシリーズの47Ωを外して行ってみる。
これで47Ωの効果が分かる。
47Ωの効果はかくも大きいのだ。
この場合は容量負荷が増えるほどにオープンゲインが8dbに沈むポイントの位相回転が進み、1600pFの場合は−180°に達してしまう。
いずれ、どの段階かで発振が必至だ。
容量負荷安定性を確保するために、47Ωは不可欠なものなのだ。
この際いにしえの抵抗負荷2段差動アンプの特性を観ておく。
低域でのオープンゲイン=61.2db、第1ポール=22KHzの素直な特性だ。
電圧ゲインの殆どを2段目差動アンプが稼ぎ、そのCobがミラー効果で拡大された容量と、初段負荷抵抗の18KΩ//2段目差動アンプの入力インピーダンスによるポールが第1ポールを形成しており、他に別途の位相補正措置を講じる必要もなく40db程度のNFBは全く安定に掛けられるオープンゲイン&位相特性となっている。
各部の電流ゲイン。
−65.2dbで2本重なっているのが初段差動アンプの電流利得。−65.2db=1/1333=0.75mSであるが、1MHz超領域まで時定数もなく破綻もない。
低域で−22dbで2本重なっているのが2段目差動アンプまででの電流利得だ。その下、低域で−32dbの線が出力R8点での電流利得だが、出力点では実際は電圧出力なのでその利得数値自体は意味がなく、周波数特性が2段目差動アンプ出力に相似である点に意味がある。
2段目までの電流利得は、−22db=1/12.6=79.4mSということになる。したがって2段目までの電圧利得は79.4mS×15KΩ=1,191倍=61.5dbとなる。上で出力点での電圧ゲイン=61.2dbであったから、終段エミッタフォロアで電圧ゲインが多少減衰することもあるから読みとり誤差を考えればピッタリだ。
それを負荷50KΩの場合の電流ゲインとして表示されたのが−32.2dbの線であるが、−32.2db=1/40.7=24.57mSなので、電圧ゲインは24.57mS×50KΩ=1,228.5倍=61.8dbと、これも読みとり誤差の範囲だ。この計算はどちらかというとどうでも良い。要は終段エミッタフォロアの周波数特性が非常に広帯域で、このアンプの第1ポールを形成しているのは2段目差動アンプのTR2SA1015のCobによるものであることがこれで明らかなのである。
何気なさそうに見えるが、実は非常に吟味された定数設定がなされていることが分かる。
(ようやく、カラーでデータを取り込む方法が分かった。(^^) < とろい。)
次に電流出力アンプ。
回路は、第2世代のGOAタイプである。
回路は「オーディオDCアンプシステム 上巻」の“MC−FM用プリアンプ”の電源電圧を±17.5Vにしたものと言えるだろうか。
スケルトン抵抗によるアッテネータが入ったイメージで50KΩを出力に負荷してある。また、NFB回路の1500pFにシリーズの抵抗はパラメトリックに0Ω、1.2KΩ、2.4KΩ、3.6KΩである。
電流出力アンプでNFB素子をドライブすると、オープンゲイン自体がRIAA特性になる。
はずなのだが、低域でのオープンゲインの上昇が不十分だ。
このため、帰還電圧が低域で減少し、帰還電圧の位相も120Hzで52°というピークを有するものとなってしまっている。
なんと、電流出力アンプの事例は最初から理想に対する現実の厳しさを知るものになってしまった(^^;
これでは電流出力アンプでNFB素子をドライブするメリットが半減し、高域のピークはないものの、低域については電圧出力アンプでドライブした場合とあまり変わらない、という結果ではないか。
問題はその原因だが、それはひとえに50KΩという低いインピーダンスのアッテネータを負荷としているためだ。
アンプが如何に電流出力(=高出力インピーダンス)でもこの50KΩが出力にパラになっていては、NFB素子のドライブインピーダンスも50KΩになってしまうのである。
これではアンプを工夫した努力が報われない。
実は、だから、理想NF型イコライザーのメリットを生かすためにはスーパーストレート型にならざるを得ない、ということなのである。
次に高域での位相の問題だが、可聴帯域以上の領域で帰還電圧の位相が回転してしまうのは高域限界を有する現実のアンプだから当然であり、この構成では10MHz超の領域で急激になっている。
1500pFにシリーズの抵抗がない場合、1MHz以上の高域でクローズドゲインが0db(=100%帰還)となるが、この場合オープンゲインが0dbとなるポイントは70MHzであり、そのポイントでの帰還電圧の位相は−210°まで回転しているからまず確実に発振することになる。
したがって、シリーズの抵抗が必要になる訳だが、1.2KΩの場合帰還電圧の位相回転は−130°である。ぎりぎりという感じである。3.6KΩであれば−100°に収まるから完全に安全だ。が、K先生の設定は大体がギリギリ。“MC−FM用プリアンプ”も1.2KΩとなっている。“MC−FM用プリアンプ”ではその出力に容量負荷対策で47Ωが挿入されているが、これなら1.2KΩを3.6KΩとすれば47Ωは省略できるように思える。その方が1個信号にシリーズの抵抗が省略出来て良さ気に思えるのだがどうだろう。
スーパーストレート型にすれば、フラットアンプまたはセカンドイコライザーの入力抵抗820KΩが出力にパラの負荷となることになる。
これならどうか。
残念ながら、これでも820KΩがパラに入ることにより、NFB回路のドライブインピーダンス≦820KΩとしかならないのだ。したがってアンプ自体の出力インピーダンスが如何に高かろうと低域でのオープンゲインの上昇は理想からは外れる。結果、70Hzに31°程度とはいえ、帰還電圧の位相に低域のピークが生じてしまう。
これが現実なのだが、相対的にはかなり理想的な状態であることも確かだ。NFB量も可聴帯域では大分一定に近づいている。低域で−10db程度の乖離しかない。
電流ドライブによる理想NF型イコライザー。電圧ドライブに比較すれば遥かに理想的であることは確かである。
なお、高域での位相状況は上の場合と同様である。
上の方で、“分配型イコライザータイプとした場合のファーストイコライザーの位相補正コンデンサーの容量は、通常型イコライザーの場合よりかなり少量で済む筈だ。な〜んて、第2世代のGOAアンプ以降はその方向に進んだ訳ですね。(^^)”と書いたので、ここで、この通常型の場合位相補正コンデンサーに10pFが必要で、分配型とした他のGOAMCプリではこれが2pFになっている理由を探る。
2pFではオープンゲインの高域ゲインが大きくなるものの帰還電圧の位相回転は変わらないので、結果1500pFにパラの抵抗が3.6KΩの場合でも位相回転が−170°に達してしまう。だからこのままNFBを掛けると発振してしまうのだ。
が、分配型であれば超高域でのクローズドゲインも42dbとなることから、位相回転も−100°に収まる。
だから、位相補正は2pFで良いのだ。ということが分かる。
分配型にすればさらに理想に近づくだろうか。
まずは低域上昇を担当するファーストイコライザー。
ここでNFB素子の定数が変わった。負荷に820KΩをパラにせざるを得ない現実に対処するため、NFB素子自体のインピーダンスを下げて理想に近づこうとしたものだ。
NFB素子のインピーダンスを下げた効果だ。
帰還電圧の位相の低域のピークは60Hzで20°のピークにとどまり、NFB量も低域で−6db以内の差に収まっている。
が、分配型ではファーストイコライザー側にNFB素子高域側による位相進み効果がないため、帰還電圧位相が20KHzで−30°の遅れとなっており、この点通常型より理想との乖離が大きいという現実も見ておく必要がある。
分配型のセカンドイコライザーはどうか。
ここでは負荷にパワーアンプが繋がるイメージで820KΩをパラに繋いである。
う〜ん、デリシアース、素晴らしい。(^^;
帰還電圧の位相はなんと低域から20KHzまで−10°以内である。NFB量も低域から50KHz程度までほぼ一定と言っていいぐらいだ。
なんとも理想的な特性になった。
高域の位相特性は、位相補正の5pFとNFB回路に入れた1.2KΩによってオープンゲイン8dbポイントで位相回転−120°と適切に補償されている。
電流出力アンプであるGOA回路による分配型イコライザーは、上のファーストイコライザーと合わせて、実に理想的ではないか。(^^)
が、周知のとおり、分配型イコライザーは捨てられたのである。歴史の海に沈んだまま二度と浮かび上がって来ることはなさそうだ。
何故か?
VGA=バリアブルゲインコントロール方式が登場したためである。と言っても間違いではない。が、正確ではない。
残念ながら、現実にはセコンドイコライザーの負荷を820KΩには出来ないのである。ここに電流出力アンプの場合に分配型イコライザー方式が捨てられざるを得ない本質的理由がある。
プリアンプはイコライズ機能の他に、音量調整機能と次に繋がる機器をドライブするための低インピーダンスドライブ能力が求められる。
これを果たすためには本当はアンプ自体は電圧出力である方が良いに決まっているのである。
これをK式では理想NFB特性を得るために電流出力アンプで行おうとするのだから、どこかで無理が生じるし、理想との乖離も生じる。
ファーストイコライザーとセコンドイコライザーの間を理想NFを得るためにスーパーストレート方式にすれば、セコンドイコライザーは音量調整機能と低負荷ドライブ能力を共に果たさなければならない。実際出力に数10KΩのボリュームやインピーダンス10KΩのチャンネルデバイダーが繋がれるのである。
であれば、負荷にパラなのは820KΩではない。まぁ10KΩとしなければならないだろう。
結果・・・
4KHzに40°のピークが生じてしまった。
帰還電圧のピークは40°以内とやや少ないが、殆ど上の電圧出力アンプでの分配型イコライザーの場合と変わらなくなってしまった。
パラに繋がる負荷インピーダンスがさらに下がるほどに一層電圧出力アンプの場合に近づいていくだろう。すなわち、電流出力アンプでの分配型イコライザー方式では高域側について電流出力でドライブすることによる理想NF型イコライザーの実現が、実際は諸般の事情で困難なのだ。という現実
これならば、分配型にするよりファーストイコライザー側にNFBイコライズ機能を集中する方がよほど合理的である。上のシミュレーション結果と比べればその方がより理想的であることが明白に分かる。
だから、電流出力アンプとなって、GOA後期にプリアンプは最終的にイコライザー+フラットアンプの構成に戻ったのだ。
分配型イコライザーは電圧出力アンプを使用していた第1世代でこそ意味があるものだったのである。
結果、電流出力アンプの出現によって、分配型イコライザーは歴史の海に沈んだのだ。
残念ではあるが、「オーディオDCアンプシステム」に多数掲載されている分配型イコライザーは、実は1.5世代のものなのだ。ということになるのである。
では、GOAのMCプリが本当に第2世代になったのはいつか?と言えば、MJ1990年6月号のNo−116“スーパー・ストレート・プリアンプ”でV・G・Aが登場したとき。
これがそのNo−116のフラットアンプのイメージである。
既に2段目のカレントミラーがフィードバック型になっている。
早速オープンゲインの周波数特性、位相特性を観る。
負荷は、当時のスケルトン抵抗によるVGAのイメージで、パラメトリックに6.1kΩ、8.3kΩ、12.2kΩ、17.8kΩ、26kΩである。
その周波数特性のシミュレーション結果は、MJ同号39ページにある図14、No−116のフラットアンプの実測周波数特性とうりふたつだ。
PSpiceシミュレーター、実に恐るべし。
その図14は高域100kHzまでだが、このシミュレーションでは1GHzまで表示させている。また図14には位相特性はない。このシミュレーターがあってはじめて観ることができた姿なのだ。
と、これは余計なことだったが、結果は、No−116のフラットアンプ、実に素直な特性を持ったアンプであることが分かる。位相補正も適切で高域まで時定数が1つしかないが如きの6db/octの減衰直線が続いている。が、位相特性を見れば1MHz以降に第2ポール以上のポールの存在が分かる。
結果、位相回転が−120°となるのは10MHz付近なので、この構成でクローズドゲイン10db設定でも安定に動作するであろうことが分かる。すなわち、50〜60dbのNFBが安定に掛かるということだ。
各部の電流ゲインを観る。
負荷はいくらでも良いのだが、10KΩとした。
2段目差動アンプの出力電流利得とカレントミラー折り返し出力電流利得がかなり良く揃っている。フィードバック型カレントミラーはやはり精度が高いようだ。
これを見ることにより、10KHz超付近の位相補正による第1ポールと、1MHz超付近のベータ遮断周波数による第2ポールの存在が分かる。
のだが、その結果としてのアンプ出力での電流利得についてはfo=22KHz程度ワンポール減衰特性になる。不思議だ。が、この結果が上の出力利得の周波数特性と位相特性なのだ。
さて、このプリアンプの出力の容量負荷耐性も観る。
このアンプにも容量負荷安定性を図るためにその出力には47Ωが挿入されている。
出力にシリーズの抵抗47Ωの先に容量負荷を繋いで超高域の位相の動向を観る。
負荷容量はパラメトリックに100pF、200pF、400pF、800pF、1600pFとこれまでの場合と同じである。
VGAなので面倒なのだが、先ず音量最低位置、すなわち負荷抵抗6.1KΩでクローズドゲイン9db設定の場合である。
上で見たとおり、位相特性−120°までの安全範囲はそもそもクローズドゲイン10dbまでだったのだからそれを9dbに設定するのはそもそも危ないと言えるのだが、案の定容量負荷が加わったこともあって100pの場合でも位相が−140°を越えてしまう。
が、それを除けば47Ωの効果で容量が増える程に安定方向になる。という結果だ。
いずれギリギリだ。作りによって発振するというK式の特徴はこの辺が理由であるわけだ。(^^;
こちらは47Ωがない場合。
いずれも−150°を越える。簡単に発振しそうだ。その意味で47Ωは必要なのだ。
これも同じだが、音量最大位置、即ち負荷抵抗26kΩで、クローズドゲイン22db時のイメージである。
負荷容量はパラメトリックに100pF、200pF、400pF、800pF、1600pFと同じ。
負荷が大きくなりゲインが大きくなるのでクローズドゲイン22dbといっても安全ではない。
が、オープンゲイン22dbポイントではみな位相は−120db以内であるから大丈夫だ。
が、47Ωをとってしまうと、少し危険方向になる。やはり47Ωは必要なのだ。
電流出力アンプの2番目は、現代の完全対称型だ。
新単行本掲載の高出力MCプリアンプをモデルにする。
現代MCプリアンプも、構成はスーパーストレート方式のRIAAEQアンプ+VGAフラットアンプである。
理想NF型イコライザー方式のMCプリアンプでは最も合理的な構成だからだ。
まず、イコライザーアンプ。
低域においてオープンゲインの伸びが不十分なため、NFB量が−8db乖離し、また、帰還電圧の位相も60Hzに28°程度のピークが生じている。
が、10Hzから20KHzの可聴帯域で帰還電圧の位相のずれはプラス28°からマイナス10°の範囲に収まっていることを見なければならない。結果、NFB量も300Hzから30KHz程度まではほぼ一定なのだ。
現実の制約の中ではかなり理想的な“理想NF型イコライザー”が実現されている。と私には思える。
が、高域特性の限界から来る位相回転の方は使用素子が同じであるから基本的にいにしえと同じだ。
初段でステップ型位相補正がなされているのもの、オープンゲインが0dbに沈む1.5MHz付近では帰還電圧の位相が−160°近くまで回転している。
う〜ん。これにはNFB回路の1500pFにシリーズの抵抗が入れられていないのだが、これでは発振してしまいそうなのだが・・・、どうだろうか。
作っていないので分からない。(^^;
実はNo−168のイコライザーをシミュレートしても位相的にはこれと大同小異の結果になるのである。が、我が実機は全く安定に動いている。ので、どこかに見落とした相違があるのかもしれない。
こちらはフラットアンプ。
負荷はバリアブルゲインコントロールのイメージでパラメトリックに1kΩ、2kΩ、4kΩ、8kΩ、16kΩ、32kΩ、64kΩである。
第2世代のGOA回路によるVGAフラットアンプはクローズドゲインを0dbまで絞ることができなかったが、最新の完全対称型回路によるVGAフラットアンプは0dbまで絞れることがこれで分かる。
この完全対称型フラットアンプについても容量負荷耐性を観ておこう。
負荷は10KΩに固定して、これもパラメトリックに100pF、200pF、400pF、800pF、1600pFを出力にパラに繋いだ場合である。
これには直列の47Ωはない。
直列の47Ωがなくとも−130°以内であるから大丈夫だ。
が、完全対称型が一般的に容量負荷に強いということではない。各種構成の仕方によるのであって、ここでは上手く容量負荷耐性が獲得されている、ということなのである。
最後に、各プラットアンプで2ウェイチャンネルフィルター(fc=600Hz)をドライブし、周波数特性、位相特性を観る。
“オーディオDCアンプ製作のすべて”第7章図66と同じになるか。
No−69
100KHz超の領域でアンプの高域限界による乖離が顕著になる。
次にNo−116
同様だが、アンプの構成が2段とシンプルなせいか、超高域も素直に思える。
高出力MCプリのフラットアンプ
100KHz超の領域での特性で波打っている。数百KHzに何らかの位相回転要素があるようだ。終段にゲインがあるせいだろうか。
(2003年5月17日)